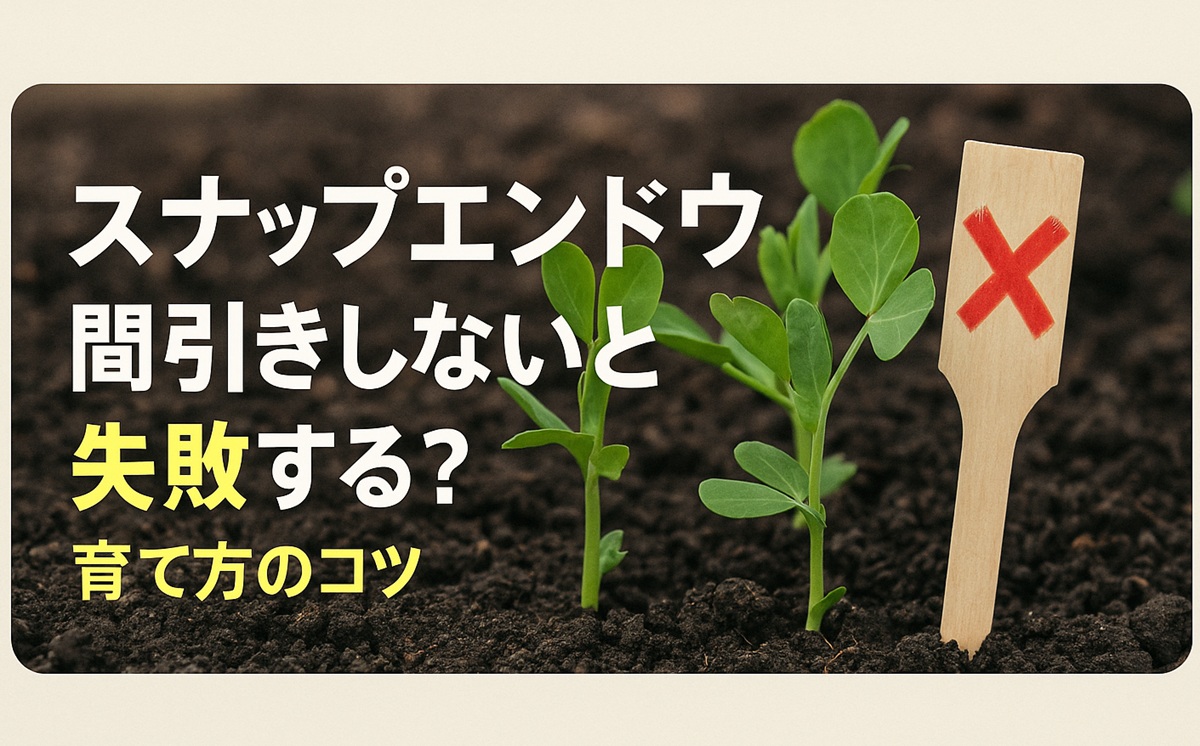採れたての美味しい野菜を味わった後、「この畑、次は何を育てよう?」と計画を立てるのは家庭菜園の大きな楽しみの一つですよね。スナップエンドウの後作には、実はたくさんの選択肢があります。後作に良い野菜を選ぶことは、次の豊かな収穫を成功させるための非常に重要なステップです。
この記事では、多くの方が悩む連作障害を避け、スナップエンドウが残してくれた豊かな土壌を最大限に活かすための土づくりのポイントを分かりやすく解説します。具体的には、定番のキュウリやトマト、夏野菜の代表格であるオクラやゴーヤ、さらにはかぼちゃ、スイカ、トウモロコシといった人気の野菜との相性を一つひとつ掘り下げていきます。
また、サツマイモのように窒素が多すぎると育ちにくい野菜との賢い付き合い方や、逆にインゲンやネギなど、後作として注意が必要な組み合わせについても詳しく触れていきます。コンパニオンプランツの考え方も取り入れ、あなたの菜園計画がさらに充実するよう、プロの視点からサポートします。
- スナップエンドウの後作に適した野菜と不向きな野菜
- 連作障害を避けるための具体的な土づくりの方法
- 各野菜を後作にする際の栽培ポイントと注意点
- コンパニオンプランツを活用した栽培テクニック
スナップエンドウの後作を成功させる基本計画
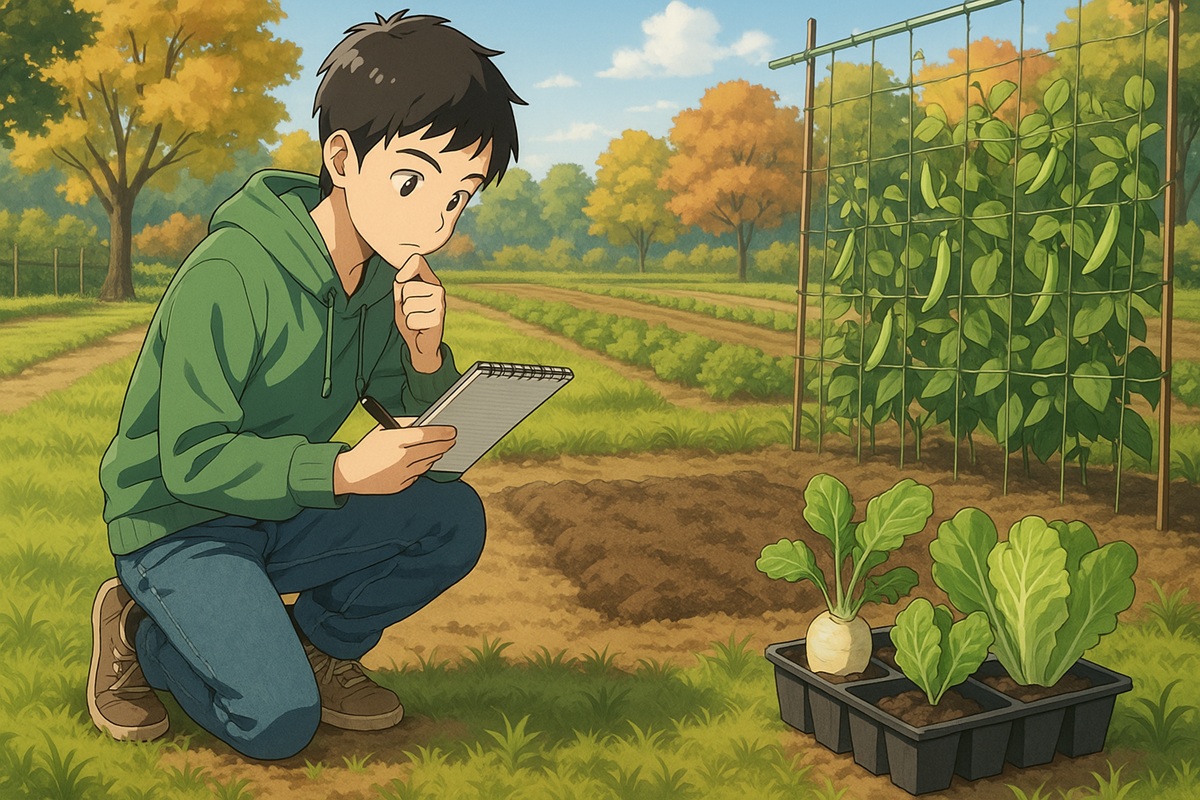
- 失敗しない後作に良い野菜の選び方
- 必ず知っておきたい連作障害の対策
- 次の収穫へ繋げる土づくりの方法
- 栽培を助けるコンパニオンプランツとは
失敗しない後作に良い野菜の選び方
スナップエンドウの収穫を終えた畑は、次なる恵みを生み出すための準備が整った状態です。後作選びで失敗しないための最も重要な結論は、「科の違う野菜を選ぶ」という一点に尽きます。これは「輪作」と呼ばれる、古くから伝わる農業の知恵であり、持続可能な家庭菜園を実現するための基本原則です。
なぜ科の違う野菜を選ぶことが重要なのでしょうか。その理由は、スナップエンドウを含むマメ科の野菜が、土壌に残してくれる特有の素晴らしい”贈り物”にあります。
マメ科の植物の根には、「根粒菌(こんりゅうきん)」という微生物が共生しています。この根粒菌は、空気の約8割を占める窒素を、植物が栄養として吸収できる形に変えて土の中に固定する「窒素固定」という驚くべき能力を持っています。この働きのおかげで、スナップエンドウを育てた後の土は、植物の葉や茎を豊かに育てるための天然の窒素肥料が蓄えられた、肥沃な状態になっています。この窒素の恩恵を最大限に活かしつつ、後述する病害虫のリスクを避けるために、異なる栄養要求を持つ、科の違う野菜を植えることが最も合理的なのです。
具体的にどのような野菜が後作として適しているか、それぞれの特徴と合わせて以下の表で確認してみましょう。
後作におすすめの野菜分類と選び方のポイント
| 分類 | 野菜の例 | ポイントと解説 |
|---|---|---|
| 葉物野菜 (アブラナ科など) | キャベツ、ハクサイ、レタス、ホウレンソウ、ブロッコリー | 葉物野菜は、光合成を行う葉を大きく育てるために多くの窒素を必要とします。スナップエンドウが残した豊富な窒素を効率よく吸収し、立派な株に成長してくれるため、非常に相性が良い組み合わせです。 |
| 実もの野菜 (ナス科・ウリ科) | トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、カボチャ、ゴーヤ | たくさんの花を咲かせ、実をつけるためには、株全体を大きく育てるエネルギーが必要です。特にナス科やウリ科の野菜は肥料を多く好むため、窒素が豊富な土壌は生育の大きな助けとなります。 |
| 根菜類 (アブラナ科・セリ科など) | ダイコン、カブ、ニンジン | スナップエンドウが比較的浅い層に根を張るのに対し、根菜類は土の深くへと根を伸ばします。これにより、異なる土層の養分を無駄なく利用できるだけでなく、土を深く耕してくれる効果も期待できます。 |
ただし、注意点もあります。例えばニンジンは、窒素分が過剰な環境では、根(食べる部分)の肥大よりも地上部の葉の成長が優先されてしまう「つるボケ」という状態になりやすいです。後作として栽培する際は、追加の窒素肥料を控えるなどの調整が求められます。
このように、次に育てる野菜の特性を深く理解し、スナップエンドウが整えてくれた土壌環境に合ったものを選ぶことが、次の成功への確実な第一歩となります。
必ず知っておきたい連作障害の対策

家庭菜園を続けていると必ず耳にする「連作障害」。これは、同じ科の野菜を同じ場所で続けて栽培することで、年々生育が悪くなる現象を指し、エンドウ類は特にこの障害が発生しやすい野菜として知られています。(参考:タキイ種苗株式会社「連作障害」)
連作障害がなぜ起こるのか、そのメカニズムは主に3つの要因が複雑に絡み合って発生します。
連作障害の三大原因
- 土壌伝染性病害の多発 特定の野菜だけを栽培し続けると、その野菜を好む病原菌(カビや細菌)や、根に寄生するネコブセンチュウなどの害虫が土壌中で増殖・蓄積します。スナップエンドウの場合、フザリウム菌による立枯病や根腐病が代表的で、一度蔓延すると防除が非常に困難になります。
- 土壌養分のアンバランス 植物はそれぞれ生育に必要な栄養素が異なります。同じ科の野菜は似たような養分を吸収するため、特定のミネラルだけが土壌から集中的に奪われ、欠乏してしまいます。一方で、特定の成分が過剰に蓄積することもあり、土全体の栄養バランスが大きく崩れてしまいます。
- 自家中毒(アレロパシー) 植物は生育過程で、他の植物の生育を抑制する化学物質を根から放出することがあります。同じ科の植物を連作すると、この物質が土壌に蓄積し、自分自身や仲間(次に植える同科の野菜)の成長を阻害する「自家中毒」状態を引き起こすことがあります。これを「いや地」とも呼びます。
この連作障害を回避するための最も基本的かつ効果的な対策は、前述の通り「輪作」を計画的に実践することです。輪作とは、畑をいくつかの区画に分け、異なる科の野菜を順番に栽培していく方法です。具体的には、一度マメ科の野菜を植えた場所では、土壌中の病原菌の密度が自然に低下するのを待つため、最低でも3〜4年、理想を言えば5年程度は再びマメ科の野菜を栽培しないように計画します。
限られたスペースで輪作が難しい場合の対策
ベランダ菜園や小さな庭では、数年単位の輪作は難しいかもしれません。その場合は、より積極的な土壌改善策を講じましょう。収穫後に土を30cm以上の深さで掘り返し、表層と深層の土を入れ替える「天地返し」は、病原菌を紫外線に当てて殺菌し、深層の未使用の土を有効活用する効果があります。
また、夏場の強い日差しを利用する「太陽熱消毒」も家庭でできる強力な対策です。土に十分な水分を与えて透明なビニールマルチで覆い、1ヶ月ほど放置することで、地温が60℃近くまで上昇し、多くの病原菌や害虫を死滅させることができます。
連作障害は、一度発生してしまうと回復に長い時間と多大な労力を要します。そのため、「転ばぬ先の杖」として、事前の計画的な対策を講じることが何よりも重要になるのです。
次の収穫へ繋げる土づくりの方法

スナップエンドウを収穫した後の土壌は、単なる”使用済み”の土ではありません。次の作物を豊かに育むための可能性を秘めた”貴重な資源”です。土づくりを成功させるカギは、スナップエンドウが残した天然の窒素を最大限に活かしつつ、次に植える野菜の種類に合わせて土壌環境を最適化することにあります。
そのための第一歩として、収穫後の株の処理方法が極めて重要になります。
後作のための具体的な土壌準備
根を土に残した後は、次の作付けに向けて土壌環境を整えていきます。
まず、日本の土壌は雨によって酸性に傾きやすい性質があります。多くの野菜は弱酸性〜中性の土壌を好むため、pHの調整は欠かせません。スナップエンドウも酸性を嫌うため、栽培前に苦土石灰などでpHを調整している場合が多いですが、作物の栽培や雨によって酸度(pH)は変化します。後作の植え付け2週間ほど前に、再度、苦土石灰や有機石灰を適量まいてよく耕し、土壌を中和させましょう。pHが適正でないと、いくら肥料を与えても植物は効率よく栄養を吸収できません。
次に、植え付けの1週間ほど前に、土壌の活力を高めるための有機物を補給します。牛ふんや鶏ふんを発酵させた完熟堆肥や、広葉樹の葉を発酵させた腐葉土などをたっぷりと投入し、土とよく混ざるように深く耕します。これらの有機物は、土壌の微生物の餌となり、土をフカフカの団粒構造に変化させ、保水性・排水性・通気性を飛躍的に向上させます。
スナップエンドウの後の土は窒素分が豊富であるため、元肥(植え付け時に施す肥料)は、窒素(N)の割合が控えめで、花や実つきを良くするリン酸(P)や、根の成長を促進し植物全体を丈夫にするカリウム(K)が多く含まれる肥料を選ぶのが、後作を成功に導くための賢い選択です。
栽培を助けるコンパニオンプランツとは

コンパニオンプランツとは、異なる種類の植物を近くに植えることで、お互いの成長に良い影響を与え合う組み合わせのことです。「共栄作物」や「共存作物」とも呼ばれ、化学農薬に頼らずに病害虫を抑制したり、土壌環境を改善したりと、多くのメリットが期待できる農法です。
この考え方は、スナップエンドウの栽培期間中だけでなく、その後作計画においても非常に役立ちます。畑全体の生態系を豊かにすることで、特定の病害虫が異常発生するのを防ぎ、より健康的で たくましい菜園環境を築くことができます。
スナップエンドウと相性の良い代表的なコンパニオンプランツ
| 植物名 | 期待できる効果 | 解説 |
|---|---|---|
| レタス・ホウレンソウ | 生育促進・環境改善 | スナップエンドウの株元に植えることで、互いの根が土壌に良い刺激を与え合います。また、スナップエンドウが成長して作る適度な日陰が、夏の強い日差しや高温に弱い葉物野菜を守るマルチのような役割を果たしてくれます。 |
| マリーゴールド | センチュウ対策 | 特定のマリーゴールドの根から分泌される物質には、多くの野菜の根に寄生して生育を妨げるネコブセンチュウの密度を減らす効果があるとされています。畑の縁や畝の間に植えることで、土壌全体の健全化に貢献します。 |
| ナスタチウム | アブラムシ対策(おとり) | 「おとり植物(トラッププランツ)」の代表例です。ナスタチウムはアブラムシを強く引き寄せる性質があるため、意図的に植えておくことで、本来の作物であるスナップエンドウへの被害を身代わりとなって防いでくれます。 |
| トウモロコシ | 天然の支柱 | これは少し上級者向けですが、トウモロコシを先に育てておくことで、その丈夫な茎をスナップエンドウがよじ登るための天然の支柱として利用できます。ネイティブアメリカンの伝統農法「スリーシスターズ」にも通じる考え方です。 |
注意すべき相性の悪い組み合わせ
コンパニオンプランツは、植物の力を借りて畑の環境を整える、奥深くも魅力的な技術です。ぜひご自身の菜園計画に取り入れてみてください。
スナップエンドウ後作の適性を野菜別で見る
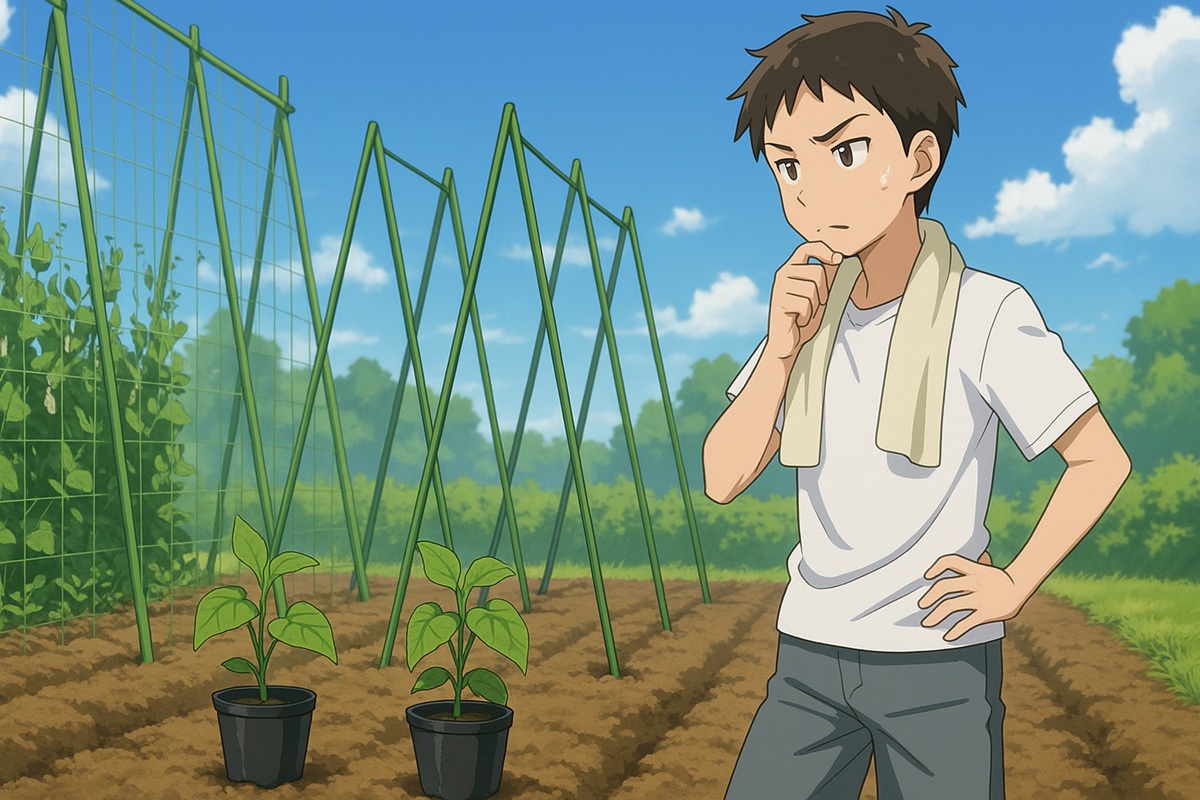
- キュウリやゴーヤを植える時の注意点
- 甘いスイカとかぼちゃを育てるコツ
- 相性抜群なトマトを栽培する方法
- 窒素を活かしたオクラの育て方
- つるぼけさせないサツマイモの栽培
- トウモロコシを植えることの利点
- インゲンなど同科の連作は避けるべき
- 相性が悪いネギを植える際の対策
キュウリやゴーヤを植える時の注意点
スナップエンドウ(マメ科)の収穫後、その場所にキュウリやゴーヤといったウリ科のつる性野菜を栽培するのは、非常に合理的で生産性の高い組み合わせです。
この組み合わせの最大の魅力は、なんといっても栽培設備をそのまま有効活用できる点にあります。スナップエンドウを育てるために設置した支柱やネットは、次につるを伸ばすキュウリやゴーヤにとって、まさに誂え向きの舞台となります。これにより、資材の準備や設置にかかる手間と時間を大幅に削減できます。さらに上級テクニックとして、スナップエンドウの収穫が終盤に差し掛かった頃に、まだ緑のカーテンとして機能している株元へキュウリやゴーヤの苗を植え付ける「リレー栽培」を行えば、限られた菜園スペースを1日も無駄にすることなく、連続して収穫を楽しむことが可能です。
土壌環境の面でもメリットは大きいです。前述の通り、スナップエンドウの根が残した窒素分は、葉を大きく茂らせながら成長するウリ科野菜にとって、初期生育を力強く後押ししてくれる貴重な栄養源となります。しかし、ここには一つ注意点があります。それは、窒素が過剰になると、つるや葉ばかりが茂って花や実がつきにくくなる「つるボケ」という現象です。これを防ぐため、元肥として加える化成肥料は窒素分が控えめなものを選び、成長の様子を見ながらリン酸やカリウムを中心とした追肥で栄養バランスを整えるのが成功のコツです。
植え付けの際は、スナップエンドウの根が残る土壌を大きく乱さないよう、苗を植える場所だけを軽く耕して植え付けます。ウリ科の野菜は根が浅く広がる性質があり、特に乾燥に弱いため、株元に敷きわらや刈草マルチを施して土壌の湿度を保ち、地温の急激な上昇を抑えることが安定した生育に繋がります。また、うどんこ病などの病気が発生しやすいため、風通しを良くするよう適切に整枝・誘引することも忘れてはいけません。
甘いスイカとかぼちゃを育てるコツ

同じウリ科の中でも、特につるを長く伸ばし、広いスペースを必要とするスイカやかぼちゃも、スナップエンドウの後作として非常に相性が良い選択肢です。
これらの野菜は、大きな果実を成熟させるために、生育期間を通じて非常に多くの養分を必要とします。そのため、スナップエンドウが土壌を肥沃な状態にしてくれることは、栽培における大きなアドバンテージとなります。科が異なるため、スイカ栽培で特に大きな問題となりやすい、土壌伝染性の「つる割病」などの連作障害のリスクを根本から回避できる点も、安心して栽培に取り組める大きなメリットです。
甘くて美味しい実を収穫するための最大のコツは、水はけと日当たりの良い環境を徹底して整えることです。スイカやかぼちゃは過湿を極端に嫌うため、水はけが悪い畑の場合は、通常よりも畝を20〜30cmほど高く作り、根が水に浸かるのを防ぎましょう。また、果実が地面に直接触れていると、湿気で腐敗したり、ナメクジなどの害虫の被害に遭いやすくなります。これを防ぐため、プラスチック製の「果実マット(玉直し・皿)」を敷いたり、わらを厚めに敷いたりといった工夫が、品質の高い収穫に繋がります。
相性抜群なトマトを栽培する方法

スナップエンドウ(マメ科)の収穫後に、トマトやナス、ピーマンといったナス科の野菜を栽培するサイクルは、多くの農業指導書でも推奨されるほど、理にかなった相性抜群の組み合わせです。
トマトは「肥料食い」「水食い」と称されるほど、多くの養分と水分を吸収して成長する野菜です。特に、茎葉を大きく広げる生育初期の段階で多くの窒素を必要とします。スナップエンドウの根に残されたゆっくりと効く窒素は、この時期のトマトの健全な成長にとって、まさに理想的なオーガニック肥料の役割を果たします。これにより、化学肥料の施用量を減らし、より環境に優しく持続可能な生育サイクルを実現できるのです。
栽培スケジュールがスムーズに連動する点も大きな魅力です。スナップエンドウの収穫が終わりを迎える初夏は、トマトの苗を植え付けるのに最適な時期とぴったり重なります。これにより、畑を遊ばせる期間(休閑期)を最小限に抑え、年間を通じた利用効率を最大化できます。
土づくりの段階で最も意識すべきことは、窒素過多を避けることです。スナップエンドウのおかげで土壌にはすでに十分な窒素が存在します。そのため、元肥や追肥では、花つきや実つきを良くする「リン酸(P)」や、根の張りを促進し、病害への抵抗力を高める「カリウム(K)」をバランス良く配合した肥料を選ぶことが極めて重要です。窒素が多すぎると、茎や葉ばかりが過剰に茂る「木ボケ(つるボケ)」状態に陥り、肝心の収穫量が減少してしまうので細心の注意を払いましょう。
スナップエンドウ栽培で使用した支柱を、そのままトマトの支柱として再利用することも可能です。ただし、トマトは草丈が高くなり、果実の重みも相当なものになるため、支柱の強度を事前にしっかりと確認することが大切です。
窒素を活かしたオクラの育て方

独特の食感が魅力で、夏の家庭菜園で人気の高いオクラ(アオイ科)も、スナップエンドウの後作として非常に合理的な選択肢と言えます。
オクラは高温を好み、夏の間じゅう次々と実をつけ続ける非常に生育旺盛な野菜です。そのエネルギーを支えるためには多くの肥料を必要とするため、スナップエンドウが土壌に残した窒素を無駄なく活用できます。生育時期の連携もスムーズで、スナップエンドウの収穫が終わる5月下旬から6月頃は、オクラの種まきや植え付けの適期です。これにより、畑を休ませることなく効率的な二毛作が可能になります。
さらに進んだ栽培方法として、農学博士の木嶋利男氏が提唱するように、オクラとエンドウを交互に不耕起(土を耕さない)で連作するという興味深い実践例もあります。これは、オクラの枯れた株を冬越しするエンドウの霜よけや支柱として利用し、土壌微生物の生態系を安定させることで、本来は連作障害が出やすいエンドウの連作を可能にするという画期的なものです。この方法は、自然の循環を活かした持続可能な農業の一つの形を示唆しています。
つるぼけさせないサツマイモの栽培

これまでは窒素を好む野菜を中心に紹介してきましたが、その逆、つまり窒素が多すぎるとかえって失敗しやすいサツマイモ(ヒルガオ科)こそ、スナップエンドウの後作に最も適した野菜の一つです。
サツマイモは、土壌中の窒素分が過剰だと、地下のイモ(塊根)を太らせるよりも、地上部のつるや葉を異常なほどに茂らせることにエネルギーを使ってしまう「つるぼけ」という生理障害を起こしやすいことで有名です。(参考:JA西春日井「サツマイモ 家庭菜園」)プロの農家が、あえて肥沃でない「痩せ地」を選んでサツマイモを栽培するのは、この性質を熟知しているからです。
ここで、スナップエンドウの残した窒素が絶妙な働きをします。化学肥料のように成分が直接的に、そして急激に効くのとは異なり、スナップエンドウの根に残された窒素は、土壌微生物の活動によってゆっくりと時間をかけて分解されます。この「穏やかに、そして持続的に効く窒素」が、サツマイモの生育にとっては過剰にならず、まさに理想的な栄養環境を提供してくれるのです。そのため、後作でサツマイモを育てる場合は、基本的に追加の肥料は不要で、むしろ元肥も追肥も一切施さない方が、形の良い美味しいイモが収穫できる可能性が高まります。
スナップエンドウの収穫が終わったら、根は抜かずに残したまま、サツマイモの植え付け用に畝を立て直します。サツマイモは過湿を嫌い、水はけの良い砂質の土壌を好むため、畝は通常よりも高く作るのがセオリーです。また、収穫したスナップエンドウのつるや葉を乾燥させ、畝の表面を覆うマルチとして利用するのも非常に良い方法です。これにより、雑草の発生を抑制し、土壌の急激な乾燥を防ぐ効果が期待できます。
トウモロコシを植えることの利点

採れたての瑞々しい甘さが格別な夏の風物詩、トウモロコシ(イネ科)も、スナップエンドウの後作として多くの利点を持つ、優れた組み合わせです。
トウモロコシは、その大きな草丈とたくさんの実を育てるために、生育期間を通じて非常に多くの窒素を必要とすることから「窒素食い」の野菜とも呼ばれます。そのため、スナップエンドウが土壌に残してくれた天然の窒素は、特に生育初期のトウモロコシにとって、力強いスタートダッシュを支える貴重な元肥となります。
この組み合わせのメリットは、土壌の化学的な側面だけにとどまりません。土壌の物理性を改善する相乗効果も期待できます。スナップエンドウの根は比較的浅い層に網目状に広がるのに対し、トウモロコシの根は太く、深くまっすぐに伸びていきます。このように根の張り方が全く異なる植物を組み合わせることで、土の様々な層に大小の隙間が作られ、土全体が自然に耕されてフカフカになり、水はけや通気性が大きく向上するのです。
もちろん、マメ科とイネ科という全く異なる科の植物であるため、連作障害の心配はありません。畑のローテーションの中にこの組み合わせを組み込むことで、土壌環境を多角的に改善し、健全な状態を維持しながら、安定した収穫を目指すことが可能になります。
インゲンなど同科の連作は避けるべき
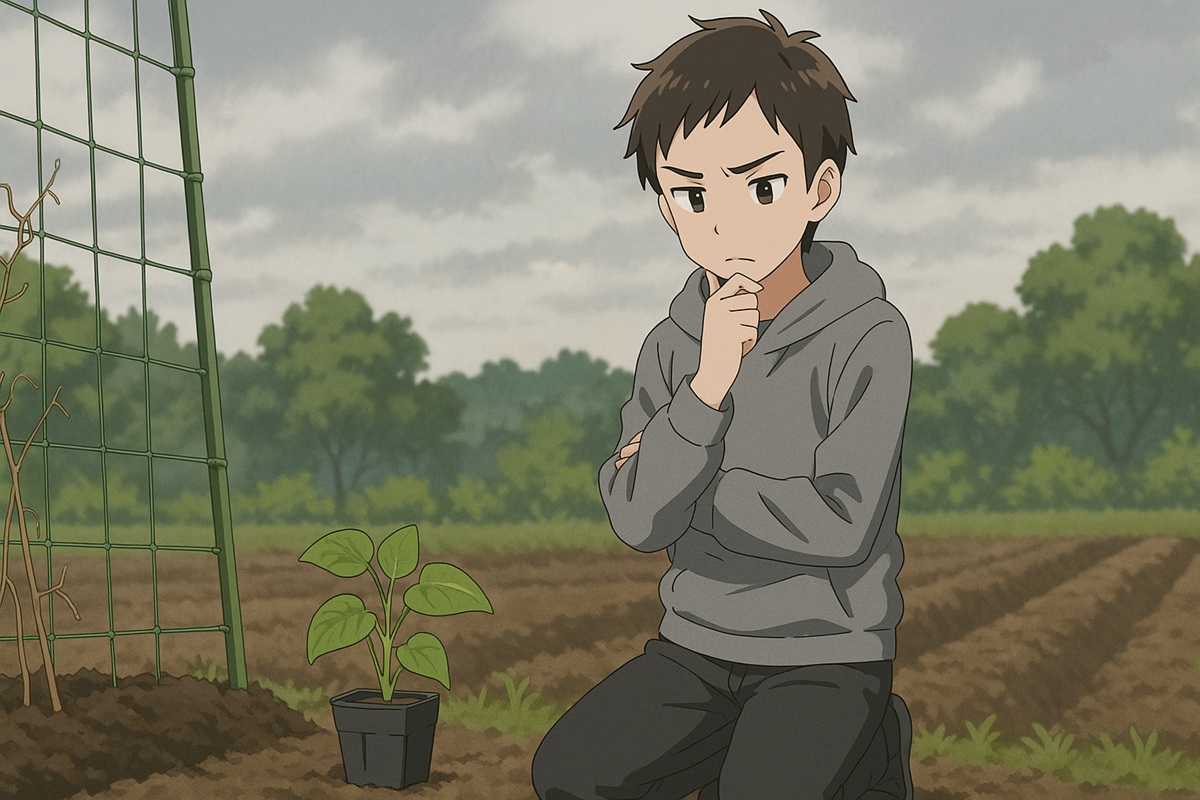
これまで様々な相性の良い野菜を紹介してきましたが、ここで家庭菜園において最も犯してはならない禁忌、つまり最悪の組み合わせについて詳しく解説します。それは、スナップエンドウを収穫した直後の場所に、インゲン、ソラマメ、エダマメ、ラッカセイといった同じマメ科の野菜を続けて植えることです。
目には見えませんが、土の中には無数の微生物が生息しています。その中には、特定の野菜に寄生して病気を引き起こす病原菌や、根に害を与えるセンチュウなども含まれます。マメ科の野菜を続けて栽培すると、マメ科を好むこれらの病原菌や害虫にとって、ご馳走が絶え間なく供給される天国のような状態となり、その数を爆発的に増やして土壌を汚染してしまいます。一度、特定の病原菌の密度が高くなってしまった土壌を元の健全な状態に戻すには、数年単位の輪作や大掛かりな土壌消毒が必要となり、多大な時間と労力がかかります。
また、栄養面でも深刻な問題が生じます。マメ科植物は窒素を供給する一方で、生育に必要な特定の微量要素(ミネラル)を土壌から吸収します。連作することで、その特定のミネラルだけが枯渇し、栄養バランスが極端に偏ってしまいます。その結果、生育不良や病気への抵抗力の低下を招くのです。「マメ科のあとには、マメ科を植えない」。これは、持続可能な家庭菜園を目指す上での絶対的なルールとして、必ず守るようにしてください。
相性が悪いネギを植える際の対策

連作には該当しませんが、ネギ、タマネギ、ニンニク、ニラといったネギ類(ヒガンバナ科、旧ユリ科)も、スナップエンドウの後作としては一般的に推奨されない組み合わせです。
これは、コンパニオンプランツの観点から、両者の相性が良くないとされているためです。ネギ類の根には、特定の微生物が共生しており、これらが作り出す抗菌性の物質が、他の植物の生育に影響を与えることがあります。特に、マメ科植物の生育に不可欠な根粒菌の働きを、この物質が阻害してしまう可能性があると指摘されています。後作として栽培する場合、スナップエンドウの株本体は既に無いため、栽培中に隣で育てるほどの強い直接的な影響はないと考えられます。しかし、土壌に残った根や微生物環境が、次に植えるネギの生育に何らかのマイナスの影響を与える可能性は否定できません。
どうしても同じ場所に植えたい場合の対策
それでも、畑の都合などでどうしても同じ場所にネギ類を植えたい場合は、リスクを可能な限り軽減するための対策を講じましょう。
最も有効な対策は、積極的な土壌改良を入念に行うことです。スナップエンドウの収穫後、できるだけ多くの完熟堆肥や腐葉土を投入し、土を深く、そして繰り返し耕して、有機物と土をよく混ぜ合わせます。これにより、土壌中の微生物の多様性(マイクロバイオーム)が豊かになり、特定の物質の影響が緩和される効果が期待できます。土壌全体の活力が向上することで、ネギ自身の抵抗力も高まります。
また、すぐに植え付けを開始するのではなく、土壌改良後、数週間からできれば1ヶ月ほど土を休ませる期間(インターバル)を設けることも、リスクを低減する上で非常に有効です。とはいえ、基本的には避けた方が無難な組み合わせであると認識しておくのが賢明です。
スナップエンドウの後作のポイントを総括
この記事のポイントをまとめます。
- スナップエンドウの後作は科の違う野菜を選ぶのが基本
- 収穫後は根を土に残して窒素を活かす
- 連作障害は輪作で計画的に回避する
- 土づくりでは石灰でのpH調整と堆肥投入が重要
- キュウリやゴーヤは支柱を再利用できるリレー栽培向き
- トマトやナス科野菜は豊富な窒素を好むため好相性
- カボチャやスイカも窒素を活かせるウリ科の好例
- オクラも生育時期が合い窒素を有効活用できる
- サツマイモは窒素過多を嫌うため後作に最適
- トウモロコシは土壌の物理性改善にも貢献する
- インゲンなど同じマメ科の連作は絶対に避ける
- ネギ類は生育阻害の可能性があるため注意が必要
- コンパニオンプランツの活用で病害虫を抑制できる
- 後作野菜に合わせて肥料の種類と量を調整する
- 計画的な栽培で一年中豊かな収穫を目指す