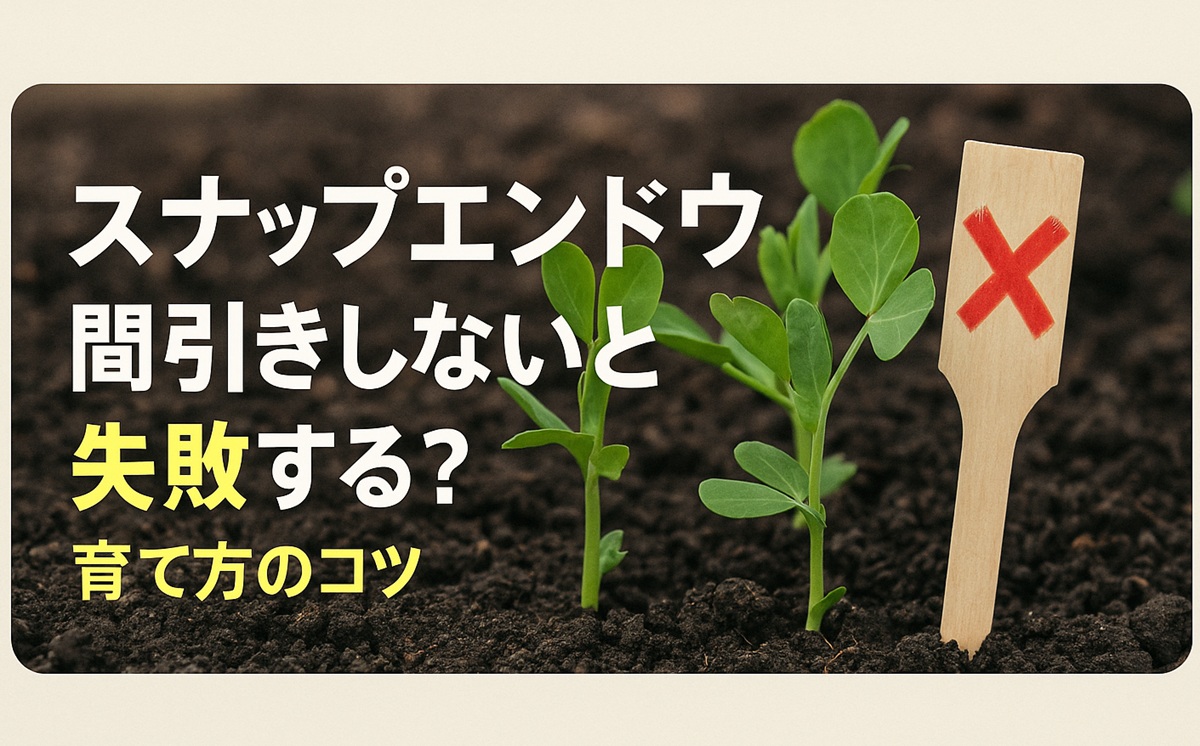家庭菜園で人気のスナップエンドウですが、「スナップエンドウを間引きしないとどうなるの?」と疑問に思ったことはありませんか。忙しくてつい作業を忘れてしまい、ほったらかしになってしまうこともあるかもしれません。
このページでは、プランター栽培や、つるなし品種の育て方、最適な種まき時期はいつか、収穫量を増やす摘心の仕方、そして基本的な間引きの仕方まで、あらゆる疑問にお答えします。さらに、間引き菜が食べれるという嬉しい情報も含め、スナップエンドウ栽培の成功に向けた知識を網羅的に解説していきます。
- スナップエンドウを間引きしない栽培のリスクやデメリット
- 基本的な間引きの手順と最適な時期
- 間引きしない場合の具体的な育て方のコツ
- 収穫量を増やすための管理方法
スナップエンドウを間引きしないリスクと可能性

- ほったらかし栽培で起こりうる問題点
- 栄養が分散?株が弱ってしまう原因
- 注意したい病害虫とその対策
- 比較解説!基本的な間引きの仕方
- 間引きの時期はいつが最適か
- 間引き菜は食べれる?美味しい活用法
スナップエンドウの栽培において「間引き」は基本作業の一つとされています。しかし、なぜその作業が必要なのでしょうか。ここでは、間引きをしない、いわゆる「ほったらかし栽培」がどのようなリスクを招くのか、そして比較対象として基本的な間引き方法についても解説します。
ほったらかし栽培で起こりうる問題点
スナップエンドウの種をまいた後、基本とされる間引き作業を行わずに「ほったらかし」の状態で育てると、いくつかの避けて通れない問題が発生する可能性があります。最も大きな問題点は、苗同士が極度に密集することで、互いの健全な成長を激しく阻害してしまうという点にあります。
植物の成長には、十分な光、水、そして土壌からの栄養が不可欠です。しかし、株が密集すると、限られたスペースの中でこれらの資源を巡る熾烈な生存競争が始まります。その結果、どの株も十分なリソースを得られず、全体的にひ弱で生育不良な状態に陥ってしまうのです。具体的には、茎は光を求めてひょろひょろと伸び(徒長)、葉は小さく色も薄くなる傾向が見られます。これは、収穫量の激減や、さやが小さくなるなど、品質の低下に直結します。
さらに、株間のスペースが失われることで風通しが著しく悪化します。空気の流れが滞ると、葉の表面が乾きにくくなり、湿気がこもりやすい環境が生まれます。このような多湿環境は、うどんこ病に代表される糸状菌(カビ)が原因の病気を爆発的に広げる原因となるため、特に注意が必要です。
栄養が分散?株が弱ってしまう原因

間引きをしない場合に株が決定的に弱ってしまう最大の理由は、有限なリソースである「栄養の分散」にあります。プランターや畑の限られた土に含まれる栄養分を、本来1〜2本の株が独占すべきところを、5本、10本といった多数の苗が分け合ってしまうのです。
植物の体を形成し、生命活動を維持するために特に重要なのが「肥料の三要素」と呼ばれる窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)です。これらの栄養素が分散し、一株あたりに供給される量が不足すると、以下のような深刻な生育障害を引き起こします。
| 栄養素 | 役割 | 不足した場合の症状 |
|---|---|---|
| 窒素(N) | 葉や茎の成長を促す(葉肥) | 葉が黄色く変色し、株全体の成長が止まる。 |
| リン酸(P) | 花や実の成長を促す(花肥・実肥) | 開花数が減り、実つきが極端に悪くなる。 |
| カリウム(K) | 根の成長を促し、病気への抵抗力を高める(根肥) | 根張りが悪くなり、病気にかかりやすく、全体的に軟弱になる。 |
このように、全ての苗が栄養不足に陥り、「共倒れ」の状態になってしまうのです。栄養と同時に日光を奪い合うため、苗は少しでも光を得ようと上へ上へと無駄に伸びる「徒長(とちょう)」を起こしやすくなります。徒長した株は、茎が細く間延びしているため、病気に弱く、少しの風でも倒れやすい非常に軟弱な状態です。結果として、収穫にたどり着くことさえ難しくなるケースも少なくありません。
スナップエンドウはマメ科植物特有の「根粒菌」と共生しており、根粒菌が空気中の窒素を土壌に供給してくれます。しかし、根粒菌の活動が活発になるのは生育中期以降であり、発芽直後の初期生育においては、土壌中の窒素が不可欠です。この最も重要な時期に栄養の奪い合いが起こることが、その後の成長に致命的な影響を与えます。
注意したい病害虫とその対策
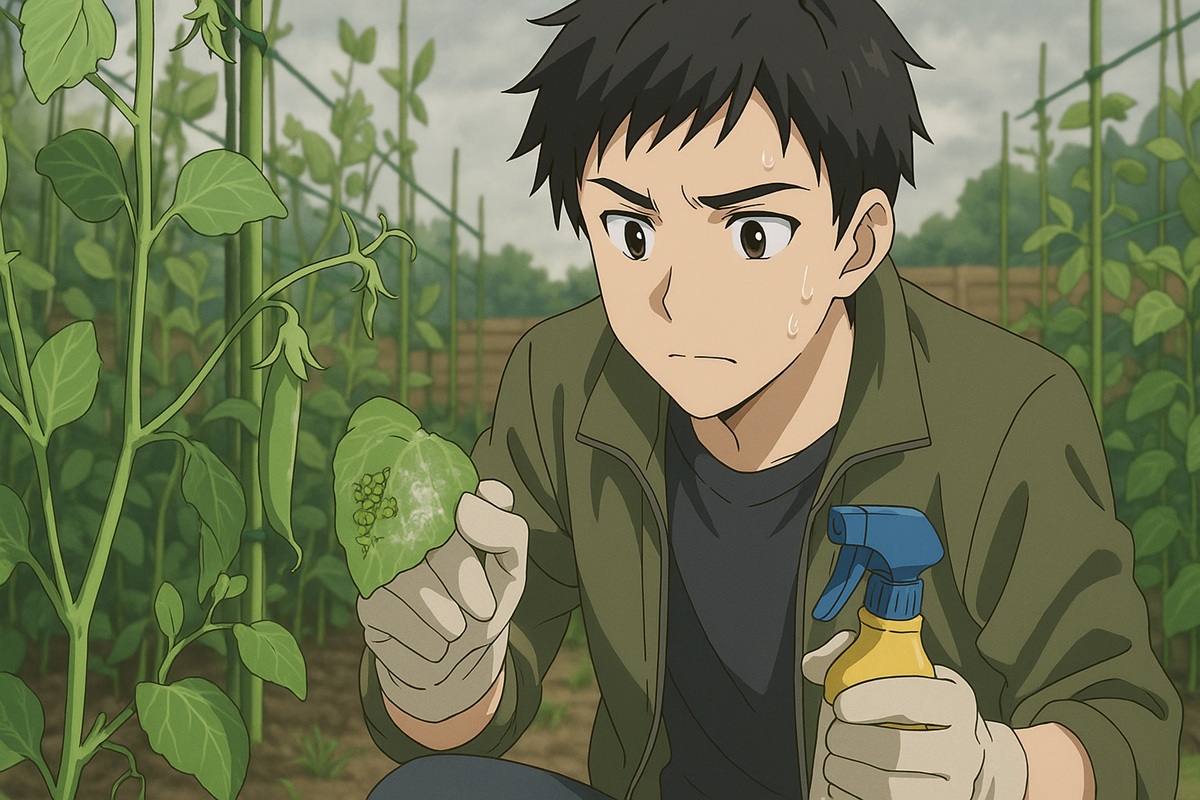
前述の通り、株が密集して風通しが悪化することは、病害虫にとって絶好の環境を提供してしまいます。ここでは特に注意すべき代表的な病害虫と、その具体的な対策について、専門的な知見を交えて解説します。
うどんこ病
葉や茎に白い粉(カビの胞子)をまぶしたように広がる、スナップエンドウで最も警戒すべき病気です。多湿環境で発生し、風によって胞子が運ばれ次々と感染します。光合成を阻害し、株全体の活力を奪い、放置すると枯死することもあります。
対策:物理的な風通しの確保、つまり間引きが最大の予防策です。発生初期であれば、病変部を切り取って処分し、被害の拡大を防ぎます。家庭でできる対策として、重曹や食酢を水で希釈したスプレーが知られていますが、効果は限定的であるため、登録のある農薬を使用するのが最も確実です。
アブラムシ
新芽や若葉の裏にびっしりと群生し、吸汁して株を弱らせる害虫です。アブラムシの排泄物は「すす病」を誘発するほか、植物ウイルス病を媒介することもあり、二次被害も深刻です。
対策:肥料、特に窒素成分の過剰投与は、葉を軟弱にしアブラムシを呼び寄せる原因となります。適切な施肥管理が予防の第一歩です。発生初期には、粘着テープで捕殺するか、牛乳スプレー(乾くとアブラムシが窒息する)などで対処します。天敵であるテントウムシを呼び込む環境づくりも有効です。
ハモグリバエ(エカキムシ)
成虫が葉に産卵し、孵化した幼虫が葉の内部を食い荒らしながら移動します。その食害痕が、まるで白い絵を描いたように見えることから「エカキムシ」とも呼ばれます。被害が拡大すると葉の光合成能力が低下し、生育不良につながります。
対策:成虫の飛来と産卵を防ぐため、種まき直後から防虫ネットで株全体を覆うのが最も効果的です。被害葉を見つけたら、葉の中にいる幼虫ごと摘み取り、畑の外で処分してください。
比較解説!基本的な間引きの仕方

間引きをしないことのリスクを具体的に理解したところで、比較対象として「基本的な間引き」の手順を改めて詳しく見ていきましょう。この作業の目的は、残す優良な株へのダメージを最小限に抑え、その後の生育を最大化することにあります。
スナップエンドウの根は、太い主根がまっすぐ下に伸びる「直根性」で、細い側根が少ないデリケートな構造をしています。そのため、苗を引き抜く際に主根を傷つけてしまうと、回復が難しく、大きな生育障害につながるため、絶対に避けるべきです。
| 項目 | 詳細な手順とポイント |
|---|---|
| タイミング | 発芽後、子葉(最初に出る2枚の葉)が完全に開き、本葉が2~3枚展開した頃が最適です。 |
| 残す苗の選び方 | 最も茎が太く、葉の色が濃く、節間が詰まってがっしりしている苗を1箇所につき1~2本選びます。ひょろひょろと徒長した苗や、葉が小さい苗は間引き対象です。 |
| 道具 | 病原菌の感染を防ぐため、事前にアルコールなどで消毒した清潔な園芸用ハサミを用意します。 |
| 手順 | 残す株の根元を押さえ、間引く株の地際(地面すれすれの部分)をハサミで切り取ります。根は土の中に残りますが、やがて分解されるため問題ありません。 |
| 作業後のケア | 残した株が風で倒れないよう、根元に優しく土を寄せ(土寄せ)、安定させます。作業後は、たっぷりと水を与えて株を落ち着かせましょう。 |
この丁寧な作業が、残した苗に全ての栄養を集中させ、日当たりと風通しを劇的に改善します。結果として、病気に強く、たくさんのさやをつける丈夫な株へと成長させることができるのです。
間引きの時期はいつが最適か

間引き作業の効果を最大限に引き出すためには、タイミングが極めて重要です。早すぎると優良な苗を見極められず、遅すぎると手遅れになる可能性があります。結論として、最適な時期は「本葉が2~3枚程度に成長した頃」に他なりません。
種から発芽して最初に出てくる双葉(子葉)は、発芽のための栄養を蓄えていた葉です。その中心から次に出てくる、スナップエンドウ本来の形をした葉が「本葉」です。この本葉が数枚出てきた段階は、苗が自らの力で成長を始めた証であり、個体差(生育の良い・悪い)が明確になる最初のタイミングなのです。
特に秋まきで冬を越す栽培方法では、このタイミングがさらに重要になります。寒さが本格化する前に間引きを終え、残した株に栄養を集中させて根をしっかり張らせることが、厳しい冬を乗り越えるための体力づくりにつながるのです。
間引き菜は食べれる?美味しい活用法

間引きでやむなく切り取った若い苗ですが、これを「間引き菜」として美味しく食べられることは、家庭菜園の大きな魅力です。栄養価も高く、捨てることなく作物を丸ごといただく素晴らしい機会となります。
スナップエンドウの間引き菜は、えぐみが少なく、豆類特有のほのかな甘みと豊かな風味が特徴です。特に若く柔らかい茎や葉先の部分は、シャキシャキとした食感も楽しめます。栄養面では、成長したスナップエンドウと同様に、ビタミンやミネラルが豊富です。例えば、文部科学省の食品成分データベースによると、成長したえんどう(若ざや)にはβ-カロテンやビタミンK、葉酸などが含まれており、間引き菜にもこれらの栄養素が凝縮されていると考えられます。
間引き菜の絶品レシピ
- 定番のおひたし:塩をひとつまみ加えた熱湯で30秒ほどさっと茹で、冷水にさらして水気を絞ります。かつお節と醤油で和えるだけで、素材の味を最も楽しめます。
- 豚肉との炒め物:ごま油で豚バラ肉と間引き菜を強火でさっと炒め、塩コショウと醤油で味付けします。シャキシャキ感が残り、ご飯が進む一品です。
- かき揚げ:玉ねぎや桜えびと一緒に、食べやすく刻んだ間引き菜を天ぷらの衣でまとめ、カラリと揚げます。豆の風味が際立ちます。
【重要】食用の際の注意点
間引き菜を食べる際は、栽培中に農薬を使用していないことが大前提です。また、観賞用として知られる「スイートピー」は同じマメ科ですが、全草に毒性があり、食べると中毒症状を引き起こすため絶対に口にしてはいけません。栽培している植物が食用のスナップエンドウであることを必ず確認してください。
間引きというひと手間が、食卓にもう一品、新鮮な彩りを加えてくれるのは、栽培者だけの特権と言えるでしょう。
スナップエンドウを間引きしない場合の育て方のコツ

- 栽培計画の基本となる種まき時期
- 密植栽培での育て方のポイント
- プランター栽培における注意点
- つるなし品種の間引きは必要か
- 収穫量を増やす摘心の仕方とは
- 支柱立てと追肥のタイミング
- スナップエンドウを間引きしないポイントを総括
栽培計画の基本となる種まき時期
スナップエンドウの栽培を成功に導くためには、全ての土台となる「種まき時期」を厳守することが何よりも重要です。スナップエンドウは生育適温が15℃~20℃という冷涼な気候を好む作物であり、この適温期間をいかに長く確保できるかが、収穫量と品質を左右します。
日本国内でも地域によって気候は大きく異なるため、お住まいの地域の気候に合わせた作型を選ぶ必要があります。
秋まき(推奨される一般的な栽培方法)
時期の目安:中間地(関東~中国・四国)では10月下旬~11月中旬。暖地(九州南部など)では11月上旬~下旬。
特徴と目的:この作型の最大の目的は、最も寒さに強い「幼苗」の状態で冬を越させることです。小さな苗のまま冬の低温に当たることで、花芽の分化が促進され(春化)、春以降の気候が温暖になるにつれて一気に成長し、多くの花を咲かせます。これにより、長期間にわたる安定した収穫が期待できます。逆に、種まきが早すぎて冬前に株が大きくなりすぎると、耐寒性が低下し、寒波で枯れてしまうリスクが高まります。
春まき
時期の目安:中間地では2月下旬~3月中旬。寒冷地(東北・北海道)では3月下旬~4月。
特徴と目的:積雪などで秋まきが物理的に不可能な寒冷地や、秋まきに失敗してしまった場合のリカバリー策として有効です。ただし、栽培期間が高温期に向かって進むため、梅雨や夏の暑さで株が弱る前に収穫を終える必要があります。そのため、秋まきに比べて収穫期間は短くなる傾向があります。
種をまいた直後は、カラスやハトなどの鳥類にとって格好の餌となります。特に直播きの場合は、発芽して本葉がしっかり展開するまで、防虫ネットや不織布のべたがけで物理的に保護する「鳥害対策」を必ず行いましょう。
間引きをしない「密植栽培」に挑戦する場合でも、この基本的な種まきスケジュールを守り、植物にとって最適な生育期間を確保することが、成功への第一歩となります。
密植栽培での育て方のポイント
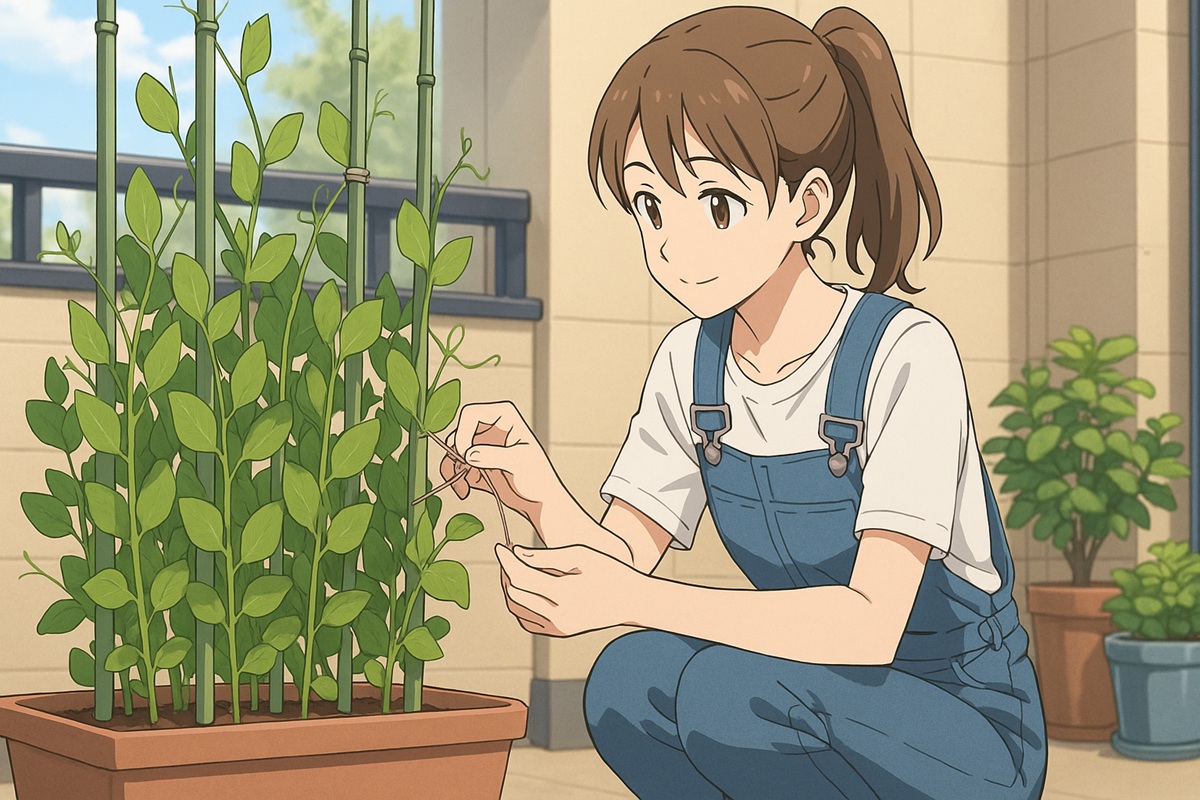
間引きを意図的に行わない栽培方法は、「密植栽培」と呼ばれます。これは単なる「ほったらかし」とは異なり、戦略的に株を密集させて育てる高等技術です。この農法の基本思想は、「一株あたりの収穫量は犠牲にするが、植え付け本数を増やすことで、圃場全体での総収穫量を確保、または向上させる」というものです。
手間を省けるメリットがある一方で、通常の栽培以上にきめ細やかな管理が求められることを理解しておく必要があります。
密植栽培を成功させるための重要ポイント
- 徹底した土づくり:多数の株が限られた土壌の栄養を奪い合うため、土づくりが最も重要です。種まきの2週間以上前に、完熟堆肥を1㎡あたり2~3kg、苦土石灰を100gほど施して深く耕し、団粒構造の豊かな土壌を作っておきます。元肥として、窒素成分が控えめでリン酸・カリウムが豊富な有機肥料をすき込んでおきましょう。
- 種まき方法の工夫:通常の栽培では1箇所に3~5粒まきますが、密植栽培では1箇所に1~2粒とします。そして、株間を5~10cm程度に設定して種をまきます。これにより、発芽後の過密状態を初期段階からコントロールします。
- 緻密な追肥・水やり計画:通常栽培よりも明らかに早く栄養と水分が枯渇します。生育状況を常に観察し、最初の花が咲き始めたタイミングで1回目の追肥、その後は2週間おきに追肥を行います。水やりも、土の表面が乾いたらたっぷりと与えることを徹底します。
- 積極的な整枝・下葉かき:密植栽培の最大の敵は、病気の原因となる風通しの悪さです。生育中に混み合ってきた枝や、黄色くなった下葉を積極的に取り除くことで、株元への風通しと日当たりを確保します。
これらのポイントを忠実に実践することで、間引き作業を省略しつつ、病気のリスクを抑え、合理的な収穫量を目指すことが可能となるのです。
プランター栽培における注意点
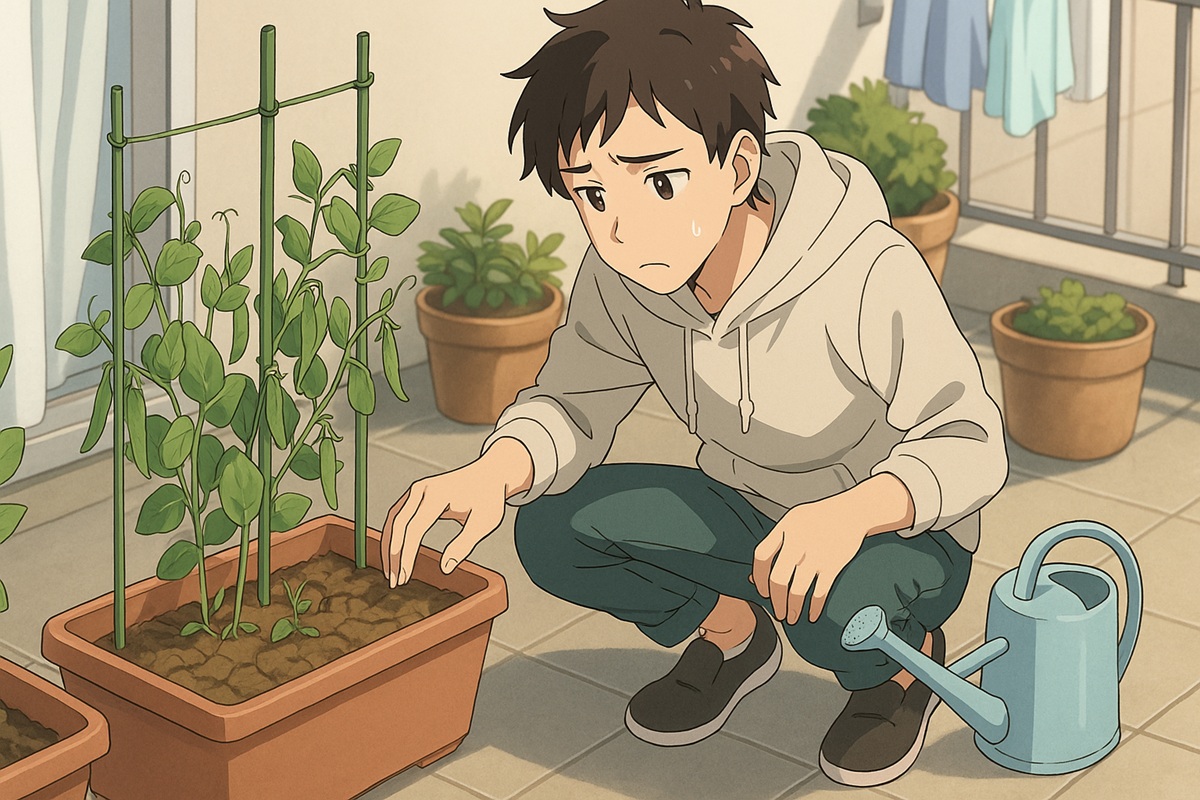
ベランダや庭先などの限られたスペースで手軽に楽しめるプランター栽培は、家庭菜園の主流です。しかし、この栽培環境は、土の量が絶対的に限られ、根の伸長範囲も制限されるという露地栽培とは全く異なる特性を持っています。
特に間引きをしない栽培を目指す場合、この「制限」を常に念頭に置いた管理が不可欠です。プランター栽培では、根詰まりを防ぎ、限られた土壌の栄養を効率的に利用させることが成功の鍵となります。
プランターというマイクロな環境だからこそ、一株一株の変化に気づきやすく、丁寧な観察が可能です。日々の観察を通じて、植物が発するサイン(葉の色、つるの伸び方など)を読み取り、きめ細かく対応することが、間引きをしないプランター栽培を成功へと導きます。
つるなし品種の間引きは必要か
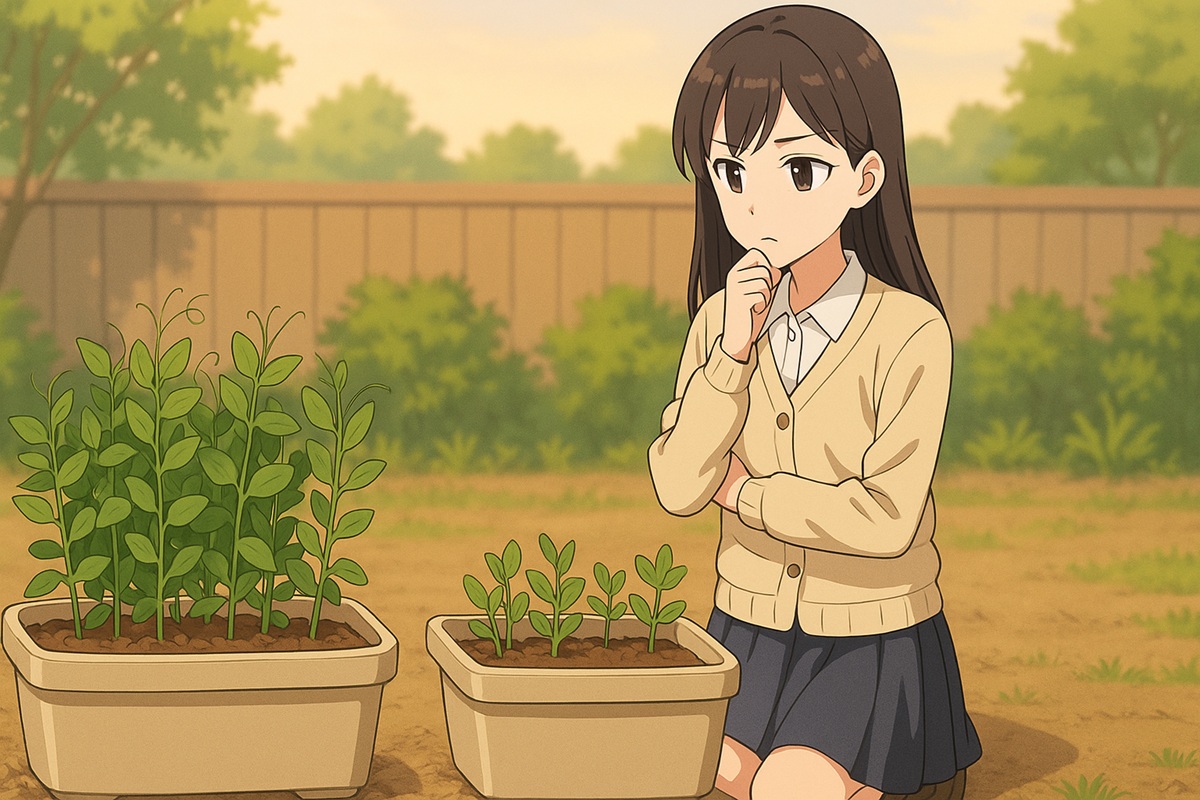
スナップエンドウには、草丈が1.5m~2m以上に伸びる「つるあり品種」と、草丈が60~80cm程度にコンパクトに収まる「つるなし品種」の2つのタイプが存在します。
つるなし品種は、支柱の設置が簡単、あるいは不要な場合もあり、管理が容易なため、特にプランター栽培や家庭菜園初心者に人気のタイプです。では、このつるなし品種の場合、間引きは本当に必要なのでしょうか。
結論から述べると、ほとんどのつるなし品種においても、基本的には間引きを行うことが推奨されています。その理由は、つるが短く伸びないだけで、株元の葉が密集し、風通しが悪くなるという根本的な問題は、つるあり品種と何ら変わらないからです。
しかし、近年の品種改良により、一部の品種では「間引き不要」を謳うものが登場しています。例えば、大手種苗メーカーであるサカタのタネが販売する「つるなしスナック2号」のように、種袋や公式サイトで密植栽培を推奨し、「間引きはしません」と明記されているケースがあります。これらは、分枝が少なく、上へ素直に伸びるように改良された、密植栽培に特化した品種です。
栽培を始める前に、必ず購入した種のパッケージに記載されている「栽培方法」や「推奨株間」を確認する習慣をつけましょう。品種の特性を最大限に活かすことが、栽培成功への一番の近道です。
もし、手元の品種情報が不明なつるなしスナップエンドウで間引きをしない栽培に挑戦するならば、株間を5cm~10cm程度確保して点まきするのが無難な選択と言えるでしょう。
収穫量を増やす摘心の仕方とは
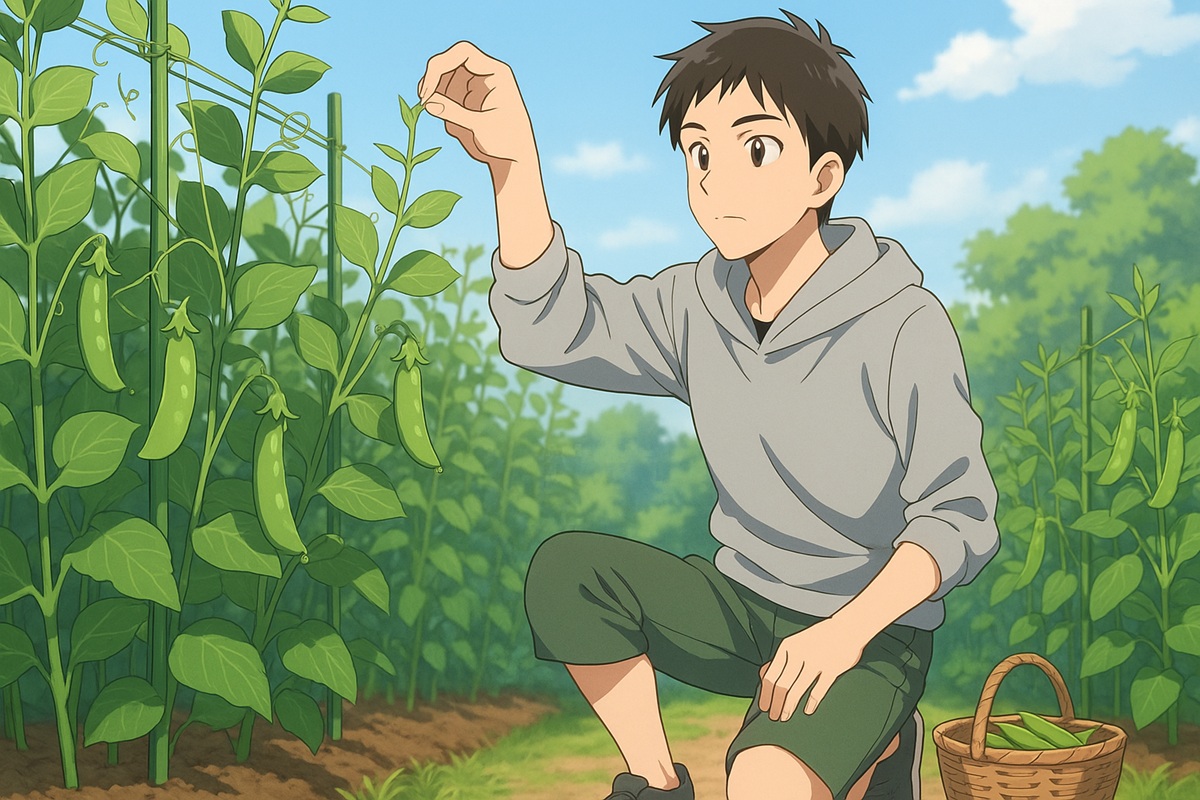
「摘心(てきしん)」は、植物の頂芽(生長点)を摘み取ることで、その下にある側芽(わき芽)の成長を促す、古くから伝わる園芸技術です。これにより、枝数を増やし、結果として花や実の数を増やして収穫量を向上させることができます。
特に、間引きをせずに株が密集し、上へ上へと伸びやすい「密植栽培」においては、摘心は収穫量を確保し、株の品質をコントロールするための極めて重要なテクニックとなります。
収穫量を最大化する摘心の手順
- 1回目の摘心(親づる):これが最も重要な摘心です。本葉が5~7枚に成長した頃、主枝(親づる)の先端を手で摘み取ります。これにより、株元から勢いの良い子づるが数本伸びてきます。
- 子づるの整枝:伸びてきた子づるの中から、生育の良いものを2~4本選び、それ以外は根元からかき取ります。これにより、選ばれた子づるに栄養が集中します。
- 2回目の摘心(子づる):選んだ子づるが支柱の高さまで伸びたら、その先端を摘心します。これにより、子づるの成長を止め、実を着けるための孫づるの発生を促します。
適切なタイミングでの摘心と整枝は、単に枝を増やすだけでなく、株全体の栄養配分を最適化し、風通しや日当たりを改善する効果もあります。まさに、収量を最大化するための積極的な栽培管理と言えるでしょう。
支柱立てと追肥のタイミング

スナップエンドウの栽培において、適切なタイミングでの支柱立てと追肥は、収穫の成否を分ける重要な管理作業です。特に、株が密集し、倒伏しやすく、肥料の消費も激しい密植栽培では、これらの作業のタイミングがよりシビアになります。
支柱立て:株が倒れる前に
タイミング:つるが伸び始め、隣の株と絡み合う前の草丈が15~20cmに達した頃が絶対的なタイミングです。これより遅れると、絡み合ったつるを解きほぐす際に茎を傷つけたり、作業効率が著しく低下したりします。
方法:畑やプランターの両端に頑丈な支柱を立て、きゅうりネットなどの園芸用ネットを張るのが一般的です。つるあり品種の場合は高さ1.8m程度、つるなし品種でも倒伏防止のために60~80cm程度の短い支柱とネットを用意すると安定します。伸びてきたつるは、こまめにネットに誘引してあげましょう。
追肥:栄養切れのサインを見逃さない
タイミング:最初の追肥は、一番花が咲き始めた頃が最適なタイミングです。これは、開花と結実に大量のエネルギー(特にリン酸)を必要とし始めるサインだからです。その後は、収穫が続く限り、2週間に1回程度のペースで定期的に追肥を行います。
肥料の選び方と注意点:前述の通り、マメ科植物は窒素過多になると「つるぼけ」を起こします。そのため、追肥には窒素(N)成分が少なく、リン酸(P)やカリウム(K)を多く含む化成肥料や有機肥料を選びます。肥料を与える際は、株の根元に直接触れないよう、株間や畝の肩にまき、軽く土と混ぜ合わせる「土寄せ」を行うと、根を傷めず効率的に吸収されます。
葉の色が薄くなってきた、花の数が減ってきた、といった症状は、肥料切れのサインかもしれません。定期的な追肥スケジュールに加え、日々の観察を通じて植物の状態を把握し、必要に応じて追肥の量やタイミングを調整することが、長期間たくさんの実を収穫し続ける秘訣です。
スナップエンドウを間引きしないポイントを総括
この記事のポイントをまとめます。
- スナップエンドウを間引きしないと株が弱り収穫量が減る可能性がある
- 原因は光や水、栄養の奪い合い
- 株の密集は風通しを悪化させ病害虫のリスクを高める
- 特にうどんこ病やアブラムシに注意が必要
- 基本的な間引きは本葉2〜3枚の頃にハサミで根元を切る
- 間引きで取り除いた若い苗は「間引き菜」として食べられる
- 間引きしない栽培は「密植栽培」という考え方
- 密植栽培は一株あたりの収量は減るが株数で補う方法
- 成功には丁寧な土づくりとこまめな管理が不可欠
- プランター栽培では深さのある容器と水・肥料管理が重要
- つるなし品種も基本的には間引きが推奨される
- 収穫量を増やすには「摘心」という技術が非常に有効
- 摘心はわき芽の成長を促し花数を増やす効果がある
- つるが伸びる前に支柱を立てネットを張る
- 追肥は花が咲き始めた頃から定期的に行う